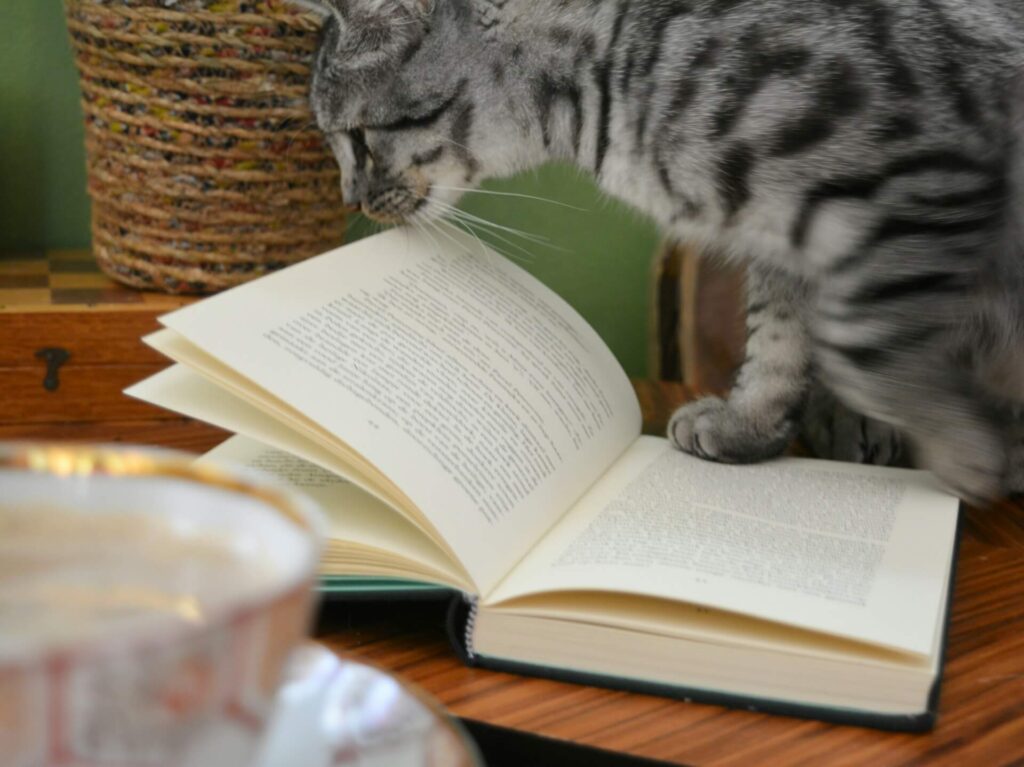

先輩に教わった通りにやっているつもりなのに、うまくいかない…

なぜ、この場面では、この介助方法を使うのかしら?
介護の現場に入ったばかりの新人さんや、現場経験を重ねてきた中堅職員さんの中にも、こんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?
実は介護技術には「根拠」があり、それを理解しているかどうかで介助の質は大きく変わります。形だけを真似しても、「根拠」が分からなければ応用できず、事故や利用者さんの不安につながることも少なくありません。
そこで【介護技術シリーズ】として、「なぜその技術を使うのか?」という「根拠」を深掘りしながら、入浴・移動・移乗・食事・排泄といった場面ごとに具体的な実践方法を紹介していきます。
今回は総論です!気楽にごらんくださいね。
新人・中堅の介護職員さんが安心して介助できるように、そして利用者さんに「任せてよかった」と思っていただけるように、一緒に学んでいきましょう!
介護技術の「根拠」とは?
人間の身体の動かし方や病気の特性などを理解したうえで、「根拠」に基づきおこなう介護は、安全で効率的かつ利用者さん本人の尊厳を守ることに繋がります。

「根拠」と「理由」を混同されることが多いので、言葉の定義を…。
「根拠」とは
その選択や判断をするための材料となる、客観的な証拠・事実そのもの。誰が見ても納得できる具体的なもの。
「理由」とは
個人的な解釈や推論。その選択をするに至った心理的な事情や背景。あくまでも主観的なものなので、客観性はもとめられていない。
介護技術に「根拠」が必要な理由3つ

利用者さんの安全と尊厳を守るため
介護技術の「根拠」に基づいた介護を行うことで、事故やケガの危険を減らし、利用者さんの命と健康を守れます。
例えば、移乗や歩行介助では、ボディメカニクスを意識することで無理な力が加わることや不安定な動作による事故を防ぐことができます。
また「利用者の同意」「意思の尊重」も大切な原則です。利用者さんのことを配慮せず職員本位に介助を進めれば、不安や不信感を生みます。残存機能を活かし、できることは自分で行っていただく自立支援こそが尊厳の保持につながります。

「説明と同意が大事だよね!」
職員の身体を守るため
介護技術の「根拠」を無視した「無理な体勢」や「急いだ介助」は、腰や肩に負担をかけ、腰痛の原因になります。正しい姿勢や支え方を理解すれば、職員の身体を守ることができ、長く働き続けられる基盤になります。

介護の仕事は好きだけど、腰を悪くして仕事を続けられなくなった仲間をたくさん見てきたわ。
チームで統一した介助を提供するため
介護技術の「根拠」を共有することは、「介護の標準化」につながります。誰が担当しても同じ質のサービスを受けられる環境は、利用者さんに安心感を与えます。

利用者さんにとって、どの職員でも同じ対応だと安心だよね!

介護の質の確保につながるのね
介護技術の「根拠」を理解していないとどうなるか

「形だけの介助」が事故につながる
形だけを真似しても目的を理解していなければ事故のリスクが高まります。
・利用者さんの身体をねじってしまいケガを招く
・ボディメカニクスを無視した結果、介助者が腰を痛める
・状況に応じた対応ができず形式的になる
利用者に不安や不快感を与える
声をかけずに触れる、乱暴な介助、命令口調などは、利用者さんに「尊重されていない」と感じさせてしまいます。

こういうことをされると嫌な気持ちになるよね。
職員自身が疲弊する
介護技術の「根拠」を理解せず「自己流」で介助をすると業務が非効率になり、クレームや同僚との衝突を招きます。結果としてストレスが溜まり、職場の雰囲気も悪化します。
介護技術の「根拠」を現場でどう活かすか
学んだことを現場で実践する
介護技術の「根拠」は「利用者の尊厳を守る」「残存能力を活かす」「安全を確保する」といった軸になります。
- 必ず名前を呼ぶ、プライバシーに配慮することで、利用者さんの尊厳を守る
- 残存機能を活用して「利用者さんができること」は自分でしていただく。
- ボディメカニクスを意識して、安全な介助と腰痛予防を両立する
これらを繰り返すことで「介助の標準化」が進み、新人も馴染みやすく、チーム全体の成長力も高まります。
まとめ
介護技術の「根拠」は、利用者さんの安全・尊厳を守るだけでなく、職員自身の身体を守り、チーム全体の介助を統一するための大切な土台です。これを理解せず「形だけの介助」に頼れば、事故や不快感を招き、職員自身も疲弊してしまいます。
大切なのは「根拠 → 実践 → 振り返り → 改善」のサイクルを続けること。新人・中堅職員の方は特に、この流れを意識するだけで確実にレベルアップできます。
行き詰まったときは「なぜそうするのか?」と心の中で問いかけてみてください。その答えが、よりよい介護へ導いてくれるはずです。

次回は介護技術の核となる「ボディメカニクス」について解説していきます!
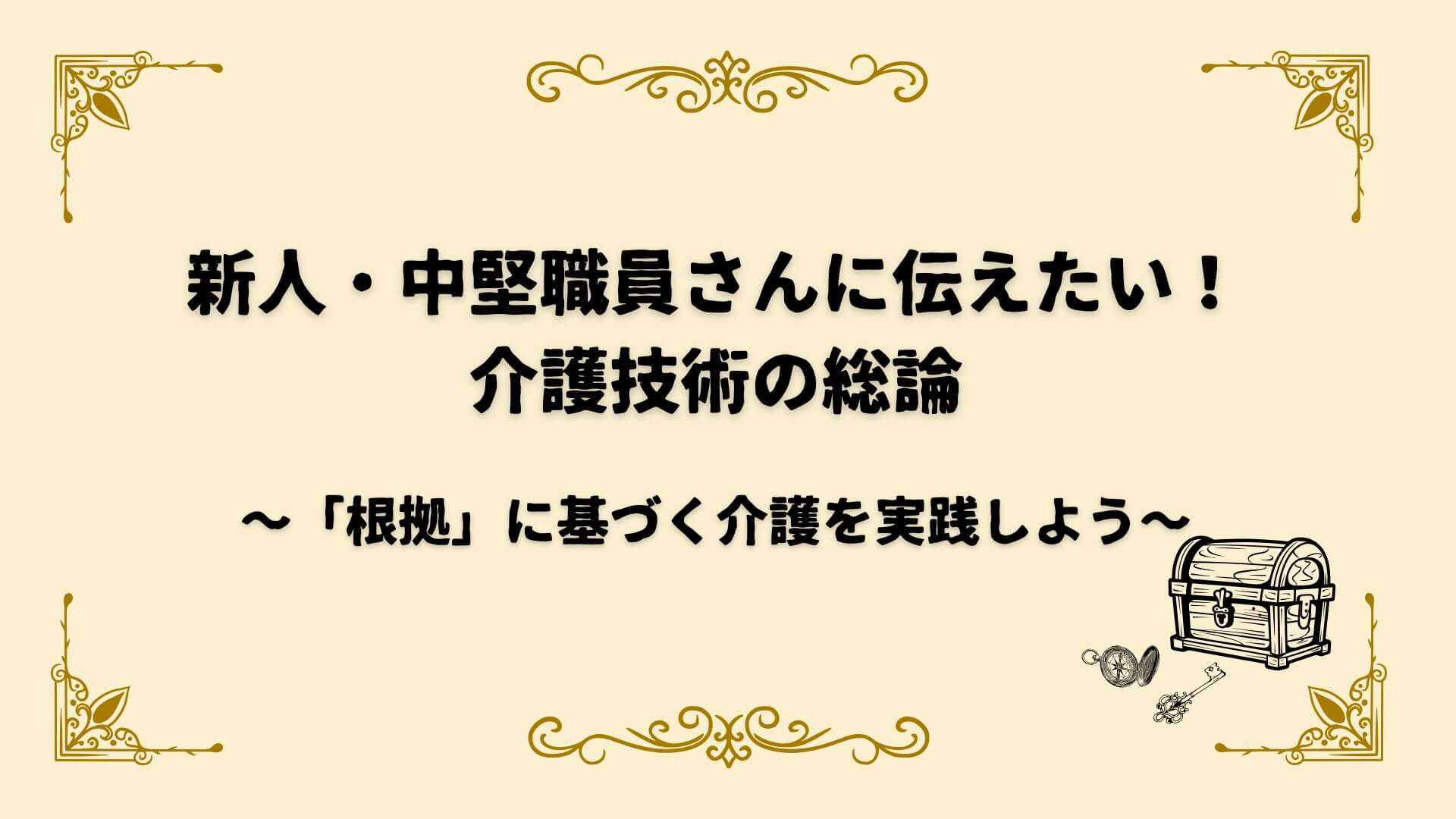
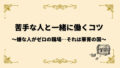
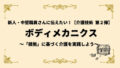
コメント