入浴介助は、介護の現場でもっとも多い介助の一つです。
単に「体を清潔にする」だけでなく、利用者さんにとってはリラックスできる貴重な時間でもあります。
ですが、入浴介助は事故のリスクも高く、ヒヤリとする場面も多いですよね。お湯の温度、移動・移乗、衣服の着脱、皮膚観察、声かけなど──気をつけることはたくさんあります。
そこで今回は、入浴介助を“根拠に基づいた介助技術”として整理し、「安全・安心・尊厳」を守るための基本と実践のポイントを解説します。
デイサービス・施設それぞれの現場での工夫も紹介しますので、ぜひ明日からの介助に活かしてくださいね。

入浴を心待ちにしている利用者さんに、お風呂を堪能していただきたい♡

利用者さんに喜んでもらえるように、「安全・安心・尊厳」を守る介護技術を一緒に見ていきましょう!
1.入浴介助の目的を整理しよう

入浴介助の目的は、大きく3つあります。
- 清潔保持と観察
- 心身のリラクゼーション
- コミュニケーションの機会
- 清潔保持と「早期発見」のチャンス
- 身体を洗い、皮膚を清潔に保つことで、様々な感染症や肌のトラブルを予防することができます。そして、入浴は皮膚の状態や身体の変化を観察する大切な機会でもあります。小さな傷や皮膚の赤み、体の異常の早期発見に役立てることも、入浴の最も大切な目的の一つです。
- 心身のリラクゼーション
- お湯に浸かることで、全身の血行促進が期待されます。また、温かいお湯は心身の緊張を自然とほぐし、利用者さんにリラックス効果やリフレッシュ効果をもたらします。
- コミュニケーションの機会
- 一般的に、入浴中は心身がリラックス状態になります。湯船に浸かっていただき、ゆっくりと会話をすることで、不安感を和らげ、精神的な安心感や満足感につながります。

お風呂に入る楽しみを感じてもらうこと。それが入浴介助の出発点ですね。
入浴介助は、単なる「作業」ではなく、利用者さんの「生活の中の楽しみや喜び」を支える援助です。
その意識があるかどうかで、利用者さんの満足度は大きく変わります。

つぎは「事前準備」「入浴介助開始〜終了」の2つのパートに分けて、それぞれのポイントを確認していきましょう!
2.入浴介助の準備
入浴介助は「準備で8割決まる」と言われるほど、事前の確認が重要です。
焦らず、慌てず、見落とさず──ここが事故防止の第一歩です。
▼体調確認
バイタル測定(体温・血圧・脈拍)を行い、入浴の可否を判断します。
血圧が高すぎる・低すぎる、発熱がある場合は無理をせず中止も選択肢に。
「いつもと違う様子」に気づく観察力が安全を守ります。
▼環境整備
浴室の温度は25〜28℃、お湯の温度は38〜40℃を目安に。
滑り止めマットや手すりの確認も忘れずに行いましょう。
▼物品準備
タオル・衣類・シャンプー・保湿剤などを、介助する位置から手が届く場所に準備。
小さな「探す時間」が、利用者さんの体を冷やすリスクになります。
▼排泄確認
入浴前に排泄を済ませていただくよう声かけをします。
入浴中にトイレに行きたくなることを防ぐための、意外と大切なポイントです。

“段取り八分”って言葉、まさに入浴介助にぴったりなんですよ。
3.入浴介助の基本手順と考え方

いよいよ利用者さんに入浴していただきますよ〜
ロードマップに沿って、解説していきます!
- 更衣
- 移動・移乗
- 洗身・洗髪
- 浴槽への出入り
- 退出・更衣・保湿

「羞恥心」への配慮を、常に忘れずにね
① 更衣
室温を25〜26℃に保ち、プライバシーに配慮します。
「脱健着患」の原則で衣服を整え、無理な姿勢を避けることが基本です。
体の観察もこのタイミングで行い、発赤や傷があればすぐに看護師へ報告します。

入浴は医療職との連携が本当に大切。情報を共有することで安心感が違います
② 移動・移乗
転倒リスクがもっとも高いのがこの場面。
滑りやすい床では介助者も利用者さんも慎重に動きましょう。
ボディメカニクスを意識し、「自分の腰を守る」姿勢も忘れずに。
浴室までの歩行が不安定な方や立ち上がりが難しい方には、シャワーチェア・リフトなどの補助具を活用します。
また、“歩ける人には歩いてもらう” ことも自立支援の一環。
必要な介助量を見極める観察力が求められます。
③ 洗身・洗髪
まず介助者自身の手にシャワーをかけ、温度を確認。
その上で「お湯加減はどうですか?」と声をかけ、利用者さんの手や足などにかけて、お湯加減がよければ体の末端から中枢にかけてシャワーをかけます。
洗髪は“指の腹”で優しく行い、力加減を確認しながら進めましょう。
洗う順番は 上から下へ、清潔な部位から汚れやすい部位へ。
皮膚が乾燥している方は泡で包み込むように洗い、摩擦を避けます。
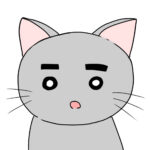
シャワーの温度は常に自分の肌で確認。確認にもせず、利用者さんの体にかけることは絶対NG!
④ 浴槽への出入り
浴槽に入る前には、再度表情の確認を行いましょう。
入浴時間の目安は10〜15分ですが、現場では5分程度で済ませることも多いです。
短い時間でも「温まった」「気持ちいい」と感じてもらうことが大切です。
出浴時は立ちくらみや転倒防止のため、「一呼吸おいてから動く」 を意識します。
⑤ 退出・更衣・保湿
入浴後は素早く体を拭き、水分を残さないようにします。
冷えを防ぐため、タオルで押さえるように拭くのがポイント。
皮膚の乾燥や発赤があれば、保湿剤でケアします。
髪を乾かしたら、再度バイタルチェックと水分補給を行いましょう。

入浴後、リラックスした利用者さんの顔を見ると、とっても嬉しくなりますね。
4.デイサービスと施設での違い

デイサービスの場合
限られた時間で複数の利用者を順番に介助するため、全体を見て動く力が求められます。
利用者さんごとに介助量を把握しておくと、スムーズな対応が可能です。
効率だけを優先せず、「リラックスできる空間づくり」 を意識しましょう。
BGMを流したり、入浴剤を使ったりと、五感へのアプローチも効果的です

“ご自分で洗えるところはお願いしますね”という声かけも立派な自立支援。
小さな一言で利用者さんの意欲が変わります。
施設(特養・老健など)の場合
施設では重度の方も多く、介助量が増えがちです。
それでも、“できる部分は自分で行う”という機会を奪わないようにしましょう。
また、入浴は皮膚観察の絶好のチャンス。
褥瘡や発赤などの早期発見はここでの気づきが鍵になります。
看護師と情報を共有し、チームでケアを行うことが重要です。

忙しいとつい職員主体になりがち。
声かけ一つで“あなたが主役ですよ”というメッセージを伝えられます。
5.入浴介助のポイントと注意点
- 声かけは「背中を洗いますね」など、動作を予告して安心感を与える
- 湯温・時間・環境に常に気を配る
- 利用者さんの羞恥心に配慮し、タオルを掛けながら介助する
- 入浴後は血圧低下や疲労に注意し、しばらく座位で休んでもらう
- 複数介助の場合は、役割分担と声のかけ方を統一する

「機械浴」、「中間浴」、「一般浴」、「シャワー浴」など入浴の方法は違っても、介助の「根拠」は同じ!
ポイントや注意点をおさえて、その介助の根拠を考えてみよう。
まとめ
入浴介助は、身体を清潔に保つだけでなく、心を癒すケアでもあります。
だからこそ、「安全」「安心」「尊厳」を守ることが介助者の大切な役割です。
根拠に基づいた介助──つまり、“なぜその動作をするのか”を理解して行うことが、利用者さんの満足につながります。
デイサービスでも施設でも、「お風呂が楽しみ」と感じてもらえるよう、一つひとつの動作を丁寧に行いましょう。
入浴介助はまさに、生活の質(QOL)を高める介助ですね!

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
次回は、排泄介助について詳しくお話します。お楽しみに!
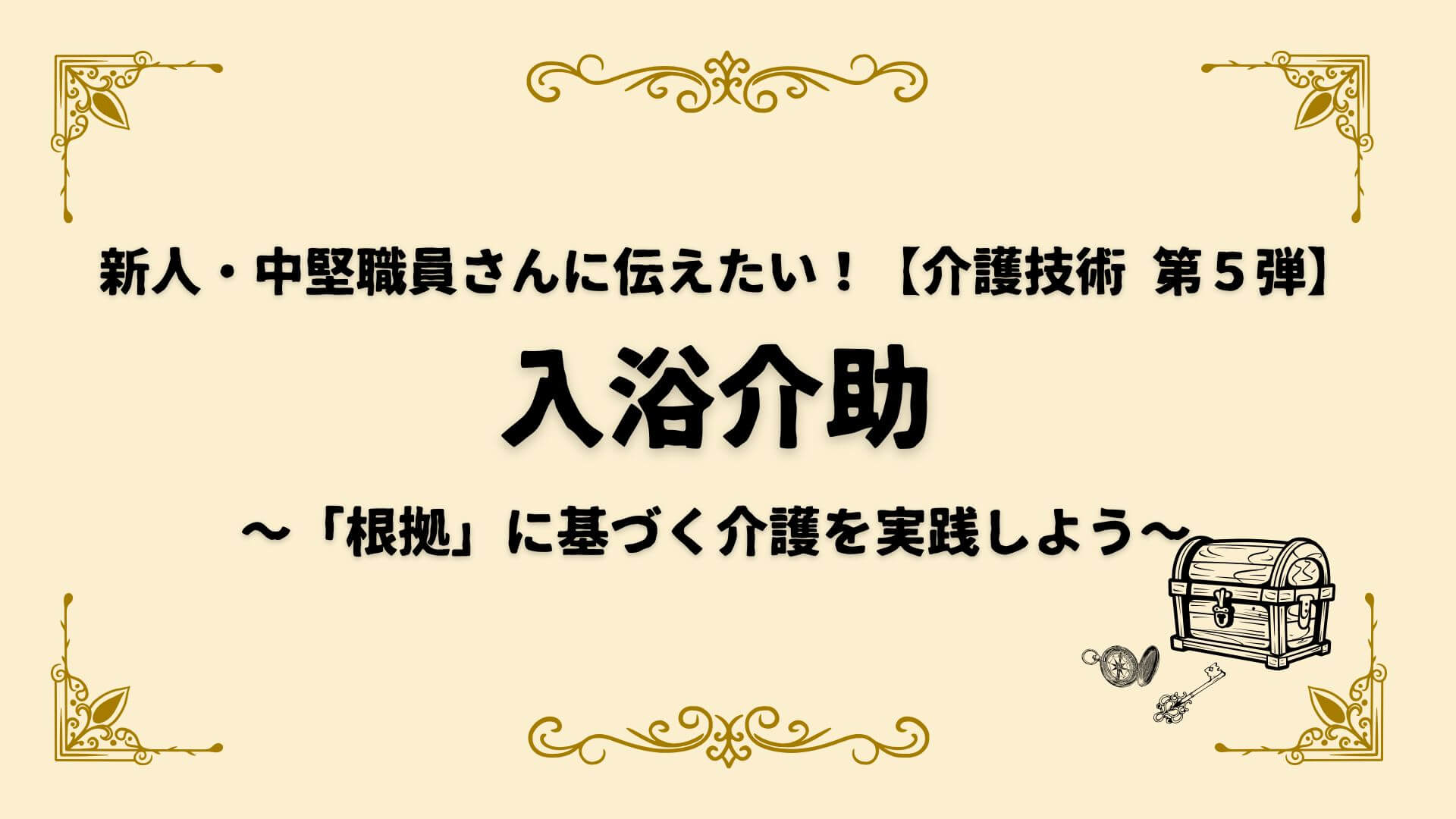
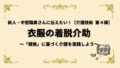
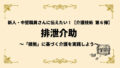
コメント