衣服の着脱介助は、一見すると「服を脱がせる・着せる」だけの単純な介助に見えるかもしれません。
ですが、利用者さんにとっては“自分らしく生活する”ための大切な動作のひとつです。
介助において、利用者さんの身体を無理に動かしてしまったり、介助の手順を誤ったりすると、痛みや羞恥心を与えてしまうこともあります。反対に、丁寧で「根拠」のある介助は、利用者さんに安心感をあたえるとともに自己肯定感を高める支援となります。
今回は、実践で意識したい衣服の着脱介助のポイントを、その根拠とともに丁寧に整理して解説します。
介助者の立ち位置や声かけ、衣服の選び方など、利用者さんが安心して自分らしく過ごせるようにするためのコツを一緒に見ていきましょう。
1.衣服の役割ってなに?
私たちは毎日、朝起きてパジャマから普段着に着替えたり、外出時に服を選んだりしています。
当たり前のように行っている「行動」ですが、実は3つの大切な意味があります。
1.身体的な意味
衣服を着ることで、体温を調節することができます。また、汗や皮脂の吸収、外傷や汚れを防ぐといった身体を安全かつ清潔に保つ役割もあります。

人類が衣類を身につけるようになった理由は、自然の中にあるリスク(気温、紫外線、植物のトゲ、毒など)から身を守るためといわれているよ。
2.精神的な意味
清潔な衣類やお気に入りの服を身に着けることで、気持ちが前向きになります。自分の好みを反映した服装は「自分らしさ」を表現する手段でもあります。

「デイサービスに行くなら…」と、利用者さんが身だしなみを気にするようになり、その結果ADLやQOLが向上するという話はよく耳にしますよ。
「生活の質」。介護を受ける方が、自分らしい生活を送ることができているか評価する概念。
「日常生活動作」。日常生活を送るうえで、最低限必要な動作のこと。
3.社会的な意味
TPOに合った服装は、社会生活をスムーズにし、信頼関係を築く上でも重要です。
他者とのコミュニケーションにおいては、言葉以上に相手に与える第一印象に大きく影響し、信頼感や親しみやすさといったメッセージを非言語的に伝えます。

「3つの意味」は当たり前のことだけど、とても大事な“介助の根拠”なんですよ。着替えは単なる作業ではなく、「その人の生活の一部」なんです。
2.衣服の着脱介助とは
衣服の着脱介助は、日常生活動作(ADL)の中でも特に「自立の象徴」とされます。自分で服を選び、着替えられることは、主体性や尊厳を守る上で非常に重要です。
介助者の役割は「全部やってあげること」ではありません。利用者さん自身ができる部分を尊重し、残された機能を活かすことが基本です。
また、着脱のタイミングや環境(室温・照明・プライバシー)への配慮も欠かせません。落ち着いた環境づくりが、利用者さんの安心感につながります。

着脱介助は、普段衣類で覆われている身体の皮膚状態を観察するチャンスでもあります。
褥瘡、かぶれ、キズ、あざなどのトラブルがないか、さりげなくチェックしましょう。
3.衣服の着脱介助で大切にしたいポイント3つ
着脱介助で大切にしたい3つのポイントは、「関節可動域」「衣服のゆとり」「自立支援」です。

1.関節可動域
麻痺や拘縮、痛みの有無によって動かせる範囲は異なります。
介助では、痛みを避け、できるだけ自然な関節の動きを促すことが大切です。

利用者さんの関節は想像以上にもろくなっているよ!
だから無理に動かすことはダメなんだよ。
2.衣服のゆとり
衣服がきついと、関節の可動域が制限されて動かしにくくなります。
また、麻痺や拘縮があって動きにくい部位は、衣服のゆとりがある段階で通しておくとスムーズです。
素材やデザイン、着脱のしやすさも選ぶ際のポイントです。

タイトで伸縮性のない衣類は、着脱介助のルールを守っていても難しいです。

麻痺のある方の上着を脱がせる時、最初に麻痺側からぬこうとして脱がせようとしてうまくいかなかった経験はありませんか?
それは「衣服のゆとりがなく、関節可動域に制限がある」からなんです。ここを意識するだけでも介助が変わりますよ。
3.自立支援
できる部分はご本人に任せること。介助の目的は“できないことを代わりにする”ことではなく、“できることを伸ばす”ことです。
介助の根底には「その人の生活を支える」という視点があります。袖を通す、ボタンを留めるなど、少しでも自分で行えるよう環境を整えることが大切です。
4.着脱介助の基本手順(片麻痺がある場合)
着脱介助の基本は「脱健着患(だっけんちゃっかん)」です。
これは、脱ぐときは健側(動かしやすい方)から、着るときは患側(麻痺側)からという原則です。

「着患脱健(ちゃっかんだっけん)」って言うこともあるよ。どっちでもOK!
1.脱衣の手順
- 健側(動かしやすい方)から脱がせる
- 麻痺側は最後にゆっくりと外す
- 関節を支えながら少しずつ進める
- 痛みがないか声をかけながら確認

健側から脱ぐことで、麻痺側の関節への負担を減らせます。無理のない姿勢で行えるため、安全で安心です。

Tシャツのようなかぶりものの時、頭はどのタイミングで脱げばよいでしょうか?

手順を根拠から考えてみるとわかるよ。
健側→頭→患側の順番だよ。
2. 着衣の手順
- 麻痺側から袖を通す
- 健側を後から通す
- 衣服がねじれないよう整える
- 着衣後に鏡で確認してもらう

麻痺側から袖を通すことで、衣服を引っ張らずに着られます。
鏡で確認することで「自分で着替えた」という達成感が得られます。

お着替えで乱れた髪の毛を整えるのもお忘れなく♡
5.介助をスムーズにするための環境づくり
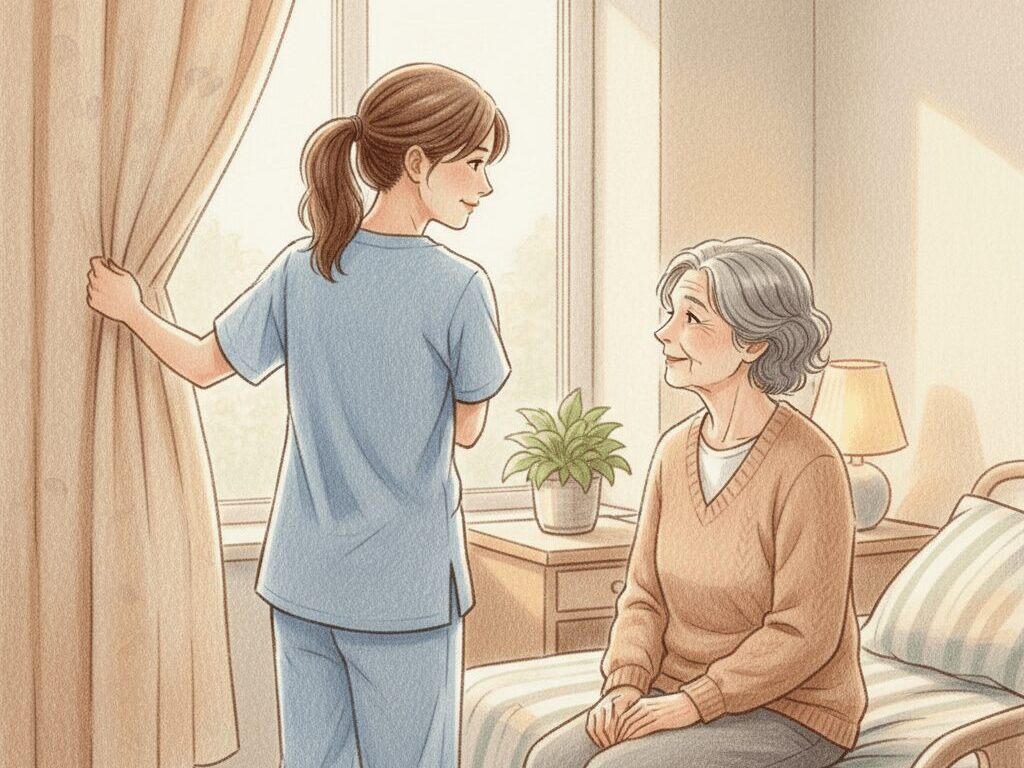
衣服の着脱は、環境によってスムーズさが大きく変わります。
以下のポイントを押さえましょう。

「動作を減らす」=「負担を減らす」。
準備をしっかり行うことで、焦らず丁寧な介助ができます。

自分が誰かに服を脱がされたりしたら、やっぱり恥ずかしいですよね。
利用者さんも同じ気持ちです。その気持ちに寄り添う姿勢が、信頼を生むんです。
6.デイサービスと施設での違い
デイサービスの場合
デイでは、入浴後や運動後といった場面で着脱介助を行うことが多いです。
利用者さんのペースを尊重し、日常生活動作の「練習の場」として支援することがポイントです。
施設(特養・老健など)の場合
施設では、麻痺や関節の拘縮により身体を動かせる範囲が限られている方、体位を変えることが難しい方の介助をすることが多く、より高度な技術力を求められます。
職員一人あたりの介護量も多いため効率を求められる場面もあるでしょう。ですが、利用者さんにとって着脱の動作ひとつひとつも関節可動域を保つためのリハビリになります。「どうすれば本人の力を引き出せるか」を常に意識して関わりましょう。
7.着脱介助のポイントとコツ

「早く着替えさせよう」と思うほど、うまくいかないもの。
ゆっくりでも“自分でやっている感覚”を大切にすると、笑顔が増えるんですよ。
8.まとめ
衣服の着脱介助は、単なる身支度のサポートではなく、「その人らしい生活」を支える介助です。
介助の目的は「早く終わらせること」ではなく、「できる力を引き出すこと」。
麻痺側・健側の順序や姿勢の安定、環境づくりなど、「根拠」を理解して行うことで、安心で質の高い介助につながります。
デイサービスでも施設でも、介助の中心は常に利用者さん。
「職員本位」ではなく「利用者さん本位」の視点を持ち、丁寧で思いやりのある介助を心がけましょう。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。
次回は【入浴介助】について詳しく解説します。お楽しみに!
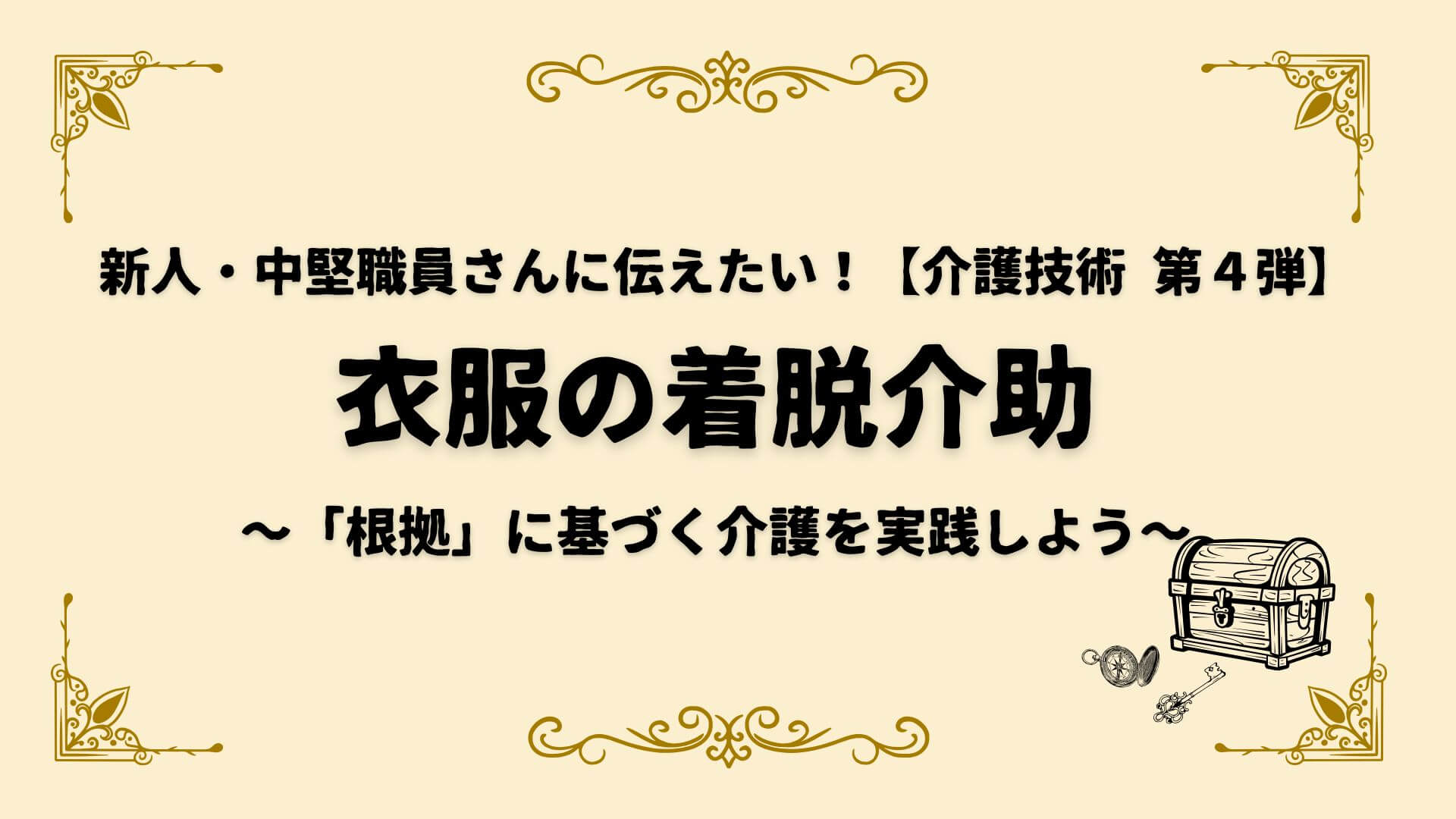
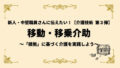
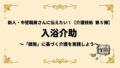
コメント