介護の現場でよく耳にする「ボディメカニクス」。新人さんからは「聞いたことはあるけど難しそう…」という声を聞きますし、中堅の方からも「実際どう活かせばいいのか迷う」「忙しくて意識できない」という悩みをよく耳にします。
でも安心してください。ボディメカニクスとは、実は「体の使い方の原理原則」をまとめたシンプルな考え方です。力任せに動かすのではなく、仕組みを理解して動かすことで、介助者の腰を守り、利用者さんも安心して動けるようになります。
今回の記事では、ボディメカニクスの8つの原則をわかりやすく解説し、実際に介護の現場でどう役立つのかを具体例とともにご紹介します。
前回の「なぜ介護技術には『根拠』が必要なのか?」に続く第二弾として、一緒に「体を楽に使う技術」を学んでいきましょう!
ボディメカニクスとは何か?
「ボディメカニクス(body mechanics)」とは直訳すると「身体力学」。人の体を効率よく動かすための原理原則をまとめた考え方です。介護現場では特に 「腰痛予防」 と 「安全に利用者さんを移動・移乗する」 ために活用されています。
「力任せではなく、仕組みを理解して介助する」こと。これを身に付けずに介助を続けていると腰痛やケガの原因になり、最悪の場合は離職につながることも少なくありません。
ボディメカニクスの8つの原則
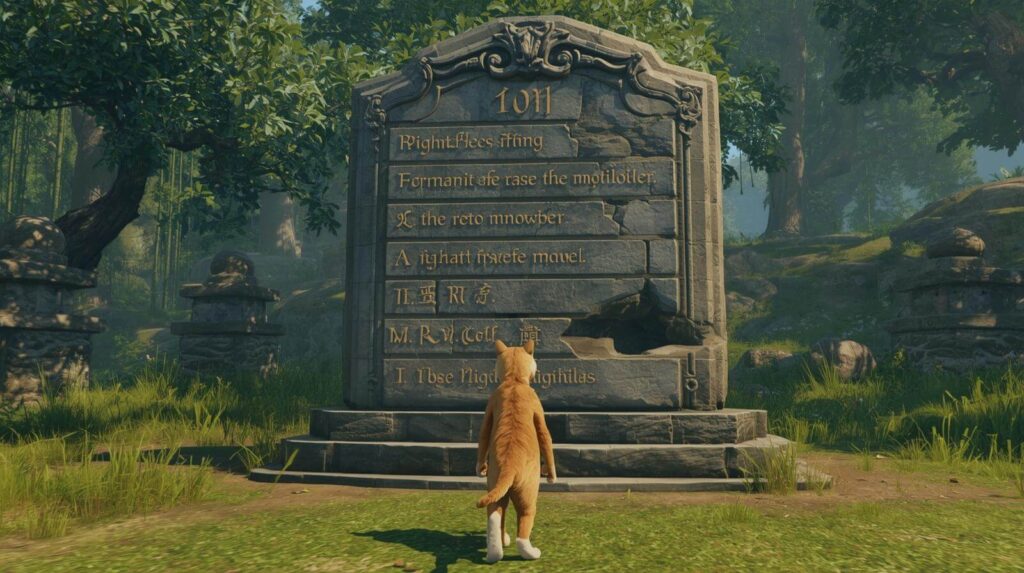
代表的なポイントは8つ。全部覚えるのは大変ですが、少しずつ意識すれば必ず現場で役立ちます。

上手な人の介助は、ぐらつかず、無駄に圧迫されず、全てが羽のように軽やかだったわ。「スッ、フワ、ストッ」みたいな。

「ボティメカニクス」を実践すると、介助する側、介助される側双方の身体的負担を減らすことができるよ!
①支持基底面を広くする
足を肩幅に広げ、片足を少し前に出すと、介助者の安定性が増します。広い土台の上に立つことで、介助中にふらつきにくくなり、利用者さんを安全に支えることができます。

意識しすぎるあまり、足を開きすぎるちゃう人もいるよ。
ポイントは、足を広げすぎないこと。肩幅より少し広めにね。
②重心を低くする
膝を曲げて腰を落とし、背筋を伸ばすのが基本です。腰だけを曲げてしまうと重心は下がらず、かえって腰痛の原因になってしまいます。

太ももの筋肉を使うイメージで膝を曲げて、重心を支持基底面積の中心に入れるようするよ。
③重心を近づける
利用者さんにできるだけ近づいて介助することで、少ない力で楽に支えることができます。身体が離れていると、腕力だけに頼ってしまい、疲れやすく危険です。

重心を近づけるときは重心を低くすることが大事。「重心を低く、近づける」だよ。
④利用者さんの身体を小さくまとめる
利用者さんに腕を胸の前で組んでいただいたり、膝を立ててもらうことで身体がコンパクトになります。摩擦が減り、動かしやすくなります。

ベッドで寝ている人の場合は、ベッドの面になるべく身体が触れないようにすると摩擦面は減ります。
⑤大きな筋肉を使う
太もも(大腿四頭筋)、お尻(大殿筋)、背中やお腹の大きな筋肉を意識して使いましょう。手や腕などの小さな筋肉に頼るよりも、効率的に力を発揮できます

大きな筋肉に軽く力をいれるだけで、身体に芯が通ったみたいに安定しますよ。
⑥水平移動を行う
利用者さんを持ち上げるのではなく、水平方向に滑らせるように動かしましょう。上下の動きは腰に大きな負担をかけるため、避けるのが基本です。

スライディングボードやスライディングシートなど福祉用具を使用するとより楽にできます。
ベッドから車椅子に移乗するときに車椅子のアームサポートを外しておくのも水平移動をしやすくなりますね。

柵を外す、ベッドの高さを調整する、福祉用具を活用する…。
ひと手間をおしまないことが、介助者と利用者さん双方の身体的負担を軽減するのよね。
⑦引く動作を意識する
押すよりも「引く」動作のほうが、より少ない力で済みます。介助者の体重移動を利用することで、さらに楽に利用者さんを支えることができます。

運動会でやる綱引きをイメージするとわかりやすいよ。
⑧てこの原理を使う
支点を意識して自分の体重を活かす方法です。ベッドや利用者さんの関節を支点にして力を加えると、効率的に動かすことができます。

最初から全部を意識するのは大変と感じる人は、「足を広げる」「重心を落とす」「近づく」の3つを意識するだけでも大きな違いを感じられますよ。
実際の介助場面での応用例
移乗介助
・利用者さんにできるだけ近づき、足を肩幅に広げて立つ
利用者さまにできるだけ近づく
足を肩幅に広げて立ち、腰を落として重心を下げる
「体を少し前に倒してください」と優しく声をかける
介助者の体重移動を活用して支える このように体全体で支えることで、腕力に頼らず安全に移乗していただけます。
入浴介助
浴槽から立ち上がるとき、腕の力だけで引っ張ってしまうと、腰を痛める原因になりやすいです。足を広げて腰を落とし、体重移動を使うことで、利用者さんも介助者の方もずっと楽にサポートができます。
デイサービスと施設での活かし方
デイサービスでのボディメカニクス活用
入浴や移動など、短時間での動作が多いデイサービスでは、「効率」と「スムーズさ」がカギになります。
ボディメカニクスを活かせば、利用者さんも「楽に動けた」と安心感につながり、サービス全体の質が向上します。
施設(入所系)でのボディメカニクス活用
介護度も重く、排泄や移乗介助の回数が多い施設では、「腰痛予防」が最も重要です。
日々の介助で、ボディメカニクスを意識すること。介助者自身の体を守りながら、長く、安心して働き続けるための大切な力になります。
まとめ
今回は介護技術シリーズ第二弾として「ボディメカニクス」を取り上げましたが、いかがだったでしょうか。
難しく考える必要はなく、まずは「足を広げる」「腰を落とす」「近づく」の3つを意識するだけで、介助はぐっと楽になります。
介助者が楽になるということは、同時に利用者さんも「安心して動ける」という信頼感につながります。大事なのは、介助をするときに「自分の体の使い方」をイメージし、利用者さんにも伝わるように説明できることです。
介護技術は体で覚えることが多いですが、そこに「なぜ」という根拠を理解して重ねると、日々の実践がもっと楽しく確かなものになります。
次回は「移動・移乗介助」について具体的に解説していきます。このシリーズを通じて「なぜこの方法を使うのか?」が自然と説明できるようになり、現場で自信を持って介助できるようになりますよ。
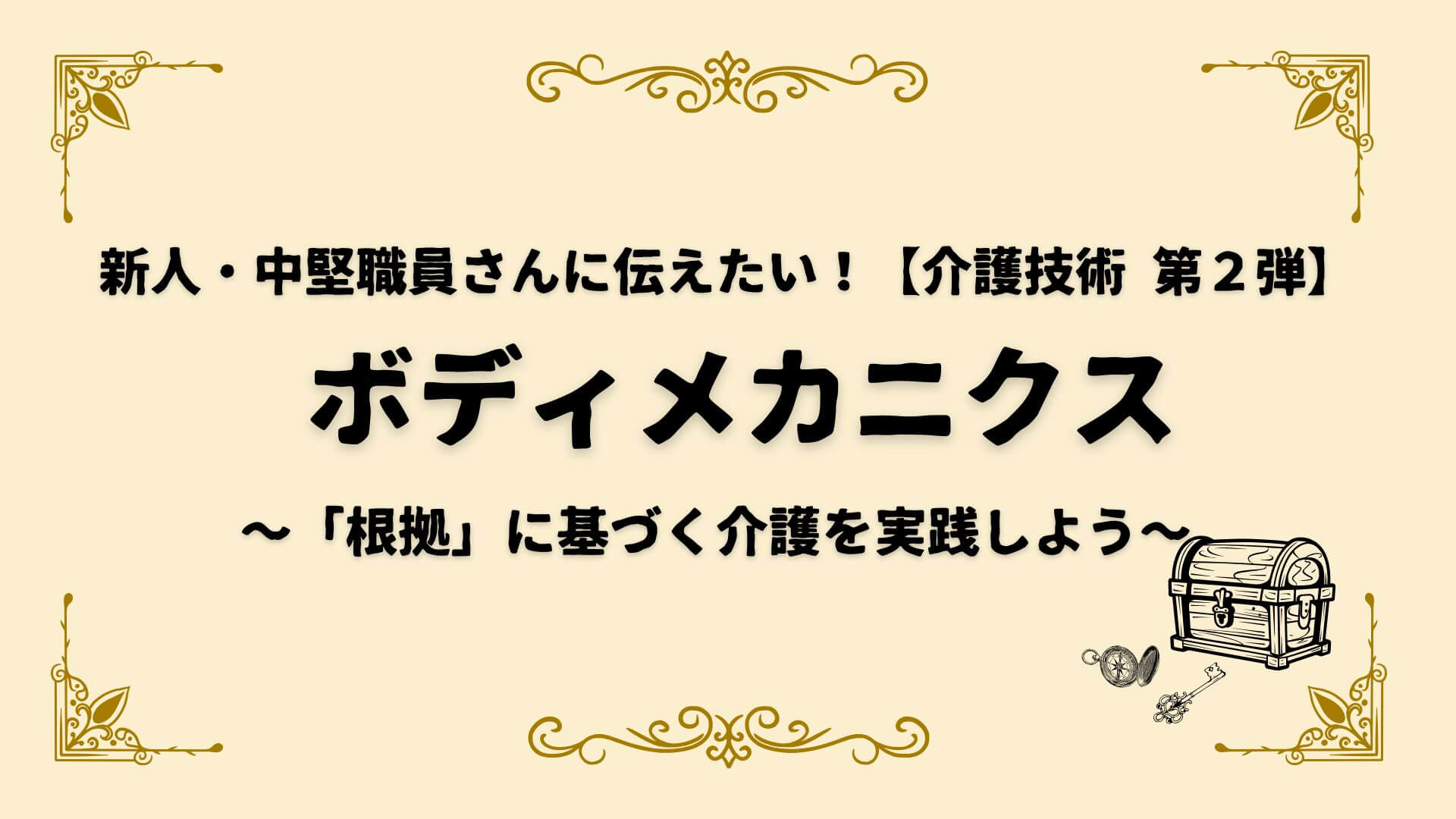
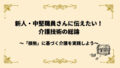
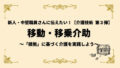
コメント