排泄介助は、介護の中でもっともデリケートなケアのひとつです。
「恥ずかしい」「情けない」と感じる利用者さんも多く、私たち介助者の言葉や態度ひとつで、尊厳を傷つけたり、嫌な気持ちにさせてしまったりすることもあります。
一方、介助者のはたらきかけ次第では、利用者さんに前向きな気持ちになっていただくことも可能です。
だからこそ、私たちは、排泄介助が「人の尊厳に関わるケア」であることを常に心に留めておく必要があります。
また、排泄介助は単なるおむつ交換やトイレ誘導ではありません。排泄の様子から健康状態の変化を早期に発見できる大切なケアでもあります。尿や便の色・形・においの変化、排泄リズムの乱れは、体調不良のサインかもしれません。
今回は、排泄介助を「恥ずかしさを取り除き、安心して排泄できるように支援するケア」として整理し、根拠を踏まえた実践ポイントを紹介します。
日常業務の中で見落としがちな“声かけ”や“環境づくり”の工夫も、一緒に見直していきましょう。
1.「排泄」とはなにか
排泄とは、体の中でいらなくなった老廃物や有害な物質を体外に出すこと。
代表的なのは排尿と排便で、人間にとって生命維持に欠かせない生理現象です。
排泄は、誰もが「人の世話になりたくない」「できる限り自分で」と思う行為です。それほどまでに、羞恥心や尊厳が強く関わっていることなのです。
介助者がこの心理を理解しているかどうかで、利用者さんの気持ちのありようは大きく変わります。
2.排泄介助の目的を整理しよう
排泄介助は、自分自身で排泄の行為や動作ができない方や排泄の機能に障害がある方を介助することです。この介助の目的は、大きく次の3つがあります。
- 身体的な健康を維持すること
- 心理的な安心感を提供すること
- 自立支援と尊厳の保持
1,身体的な健康を維持すること
尿や便を適切に排出して、感染症や皮膚トラブル(かぶれ・褥瘡)を防ぐ。

排泄物が皮膚に触れている時間を短くすることが大切だよ
2, 心理的な安心感を提供すること
「恥ずかしい」という気持ちを軽減し、「ここなら、この人なら安心して任せられる」と感じてもらう。

自分を「される立場」に置き換えて考えると、自ずと取るべき態度、言葉がイメージできるよ。

怒らない、急かさない、恩着せがましくない、介助が乱暴じゃない、口下手でもいいから目は笑っていてほしい…と私は思うので、理想の介護を目指して頑張るにゃん。
3,自立支援と尊厳の保持
利用者さんの残存能力を最大限に活かすことと、観察にもとづく援助によって、「自分でできた」という成功体験を積み重ねてもらう。

たとえば、「排泄コントロール」や「排泄のタイミング」で声掛けすることによって、下痢・便秘や失禁を防ぐことができます。

排泄介助って、“恥ずかしいこと”を“安心できること”に変えるケアなんですよね。
3.排泄の仕組みと観察のポイント
加齢や疾患による膀胱や肛門の筋力低下、神経伝達の遅れなどが原因で、「尿意・便意を感じにくい」「我慢できない」「出にくい」といった排泄トラブルが起こりやすくなります。
利用者さんの排泄物を観察することは、体調の変化や病気のサインをいち早く発見し、ケアを改善するための重要なヒントになります。
腎臓で血液から不要な成分がろ過されて、尿が作られます。つくられた尿は膀胱にためられ、尿意を感じて排出する流れです。
食べ物が消化・吸収された後の不要なものが大腸で水分を吸収されて便となり、便意を感じて排出されます。

おむつ交換は観察のチャンスです。
少しの変化でも“あれ?”と思ったら、看護師さんに共有しておきましょう。

排泄前後の利用者さんの行動からは、”排泄のタイミング”を掴むヒントが隠されている?!

利用者さんのだす「非言語的サイン」もしっかりキャッチして、介助を最適化していきたいね。
4.排泄介助のポイント


トイレでの排泄介助を中心に解説していきます
① 声かけとプライバシーの配慮
「トイレ行きましょうか?」よりも、「そろそろお手洗いの時間ですね」といった言葉のほうが尊重を感じやすいです。
カーテンやパーテーションを閉め、他の利用者の視線を遮る工夫を忘れずに。
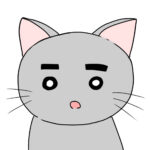
職員本位の声かけはNG。
利用者さんに“安心”を感じてもらえる声かけを意識しましょう

周りの人に聞こえないような声の大きさを心がけて
② トイレ誘導(歩行・車いす)
- 歩行介助では、重心を近づけてゆっくり体重移動。
- 車いすの場合は、フットレストを上げてブレーキ確認を必ず。
- トイレの入り口や通路は狭くなりやすいため、周囲の安全確認を丁寧に行います。
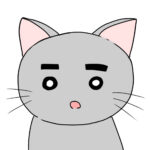
利用者さんの体調によっては、いつもできることができないことも。特に立位が不安定ないこともあるので
③ 衣服の着脱と排泄介助
「脱健着患(脱ぐときは健康側から、着るときは患側から)」の原則を守りながら、衣類やおむつを整えます。利用者さんができる範囲で動作できるよう、片手で支え、片手で手伝うのが理想です。
羞恥心に配慮し、「大丈夫ですよ」「終わりましたら教えてくださいね」と声を添えることで安心感が増します。
④ 排泄後の整容・記録
陰部洗浄やおむつ交換の際は、摩擦を避けてやさしく拭き取り、乾燥や発赤を確認します。
使用済み物品の処理・手指衛生を徹底し、排泄記録を残します。

陰部や臀部を清拭するときは、こすらず“ポンポン”と軽くたたくように拭くのがポイントですよ
5.排泄介助で大切にしたい考え方

尊厳を守る
排泄は「人としての尊厳」に関わる行為です。できるだけトイレで排泄してもらう支援が基本です。
おむつ対応が必要な場合でも、言葉づかいや動作の丁寧さで印象は大きく変わります。
自立を支える
介助量を最小限にし、「できることを奪わない」姿勢が大切です。たとえば…
- 衣服の上げ下げを一部自分で行う
- 立ち上がりだけ介助して、あとは見守る。といった支援で「できた」という自信を積み重ねます。

“待つ勇気”も大事。少しの時間で、利用者さんの自立につながることも多いんですよ。
6.デイサービスと施設での違い
デイサービスの場合
通所系サービスの場合、滞在時間が限られていることもあり、「入浴前・昼食後・帰宅前」等の時間に合わせて誘導することが多いです。
一人ひとりのペースを尊重し、流れ作業にならないよう、くれぐれも注意しましょう。
トイレまでの距離が長い場合は、途中での見守りや声かけを忘れずに。
施設(特養・老健など)の場合
24時間という時間枠の中で対応していく必要があります。排泄リズムが概ね一定の方もいれば、不規則な方も多く、個別対応力が求められます。
介護度の高い方が多いため、立位の保持が厳しい方の介助やトイレ(ポータブルトイレ)への移乗介助の技術も合わせて必要となります。
おむつ交換時には「体位変換」「皮膚保護」「フィッティング」が重要で、介助の質が快適さや褥瘡リスクに直結します。

施設では排泄介助の回数が多い分、慣れで雑になりがち。だからこそ、1回1回を丁寧に。利用者さんの“安心”はそこから生まれます。
7.排泄介助のポイントまとめ
- 声かけとプライバシー配慮で“恥ずかしさ”を軽減
- 観察の目を持ち、体調変化を早期発見
- できることを奪わず、自立支援を意識
- 清潔保持・感染予防を徹底
- 記録・報告でチーム連携を強化

“丁寧な排泄介助”って、結局“その人を大事にする介助”なんですよね。
まとめ
排泄介助は、介護の中でもっとも人の尊厳に関わるケアです。
だからこそ、「早く・効率的に」よりも「安心して・自分らしく」を意識することが大切。
一人ひとりに合わせた声かけ、環境整備、観察が利用者さんの安心と健康を守ります。
排泄介助を“恥ずかしいケア”ではなく、“尊厳を支えるケア”として自分の介助を見直してみましょう。利用者さんの笑顔や信頼につながっていきますよ。

最後までお付き合いいただきありがとうございました
次回は、介護技術シリーズ第7弾「食事介助」についてお話しします
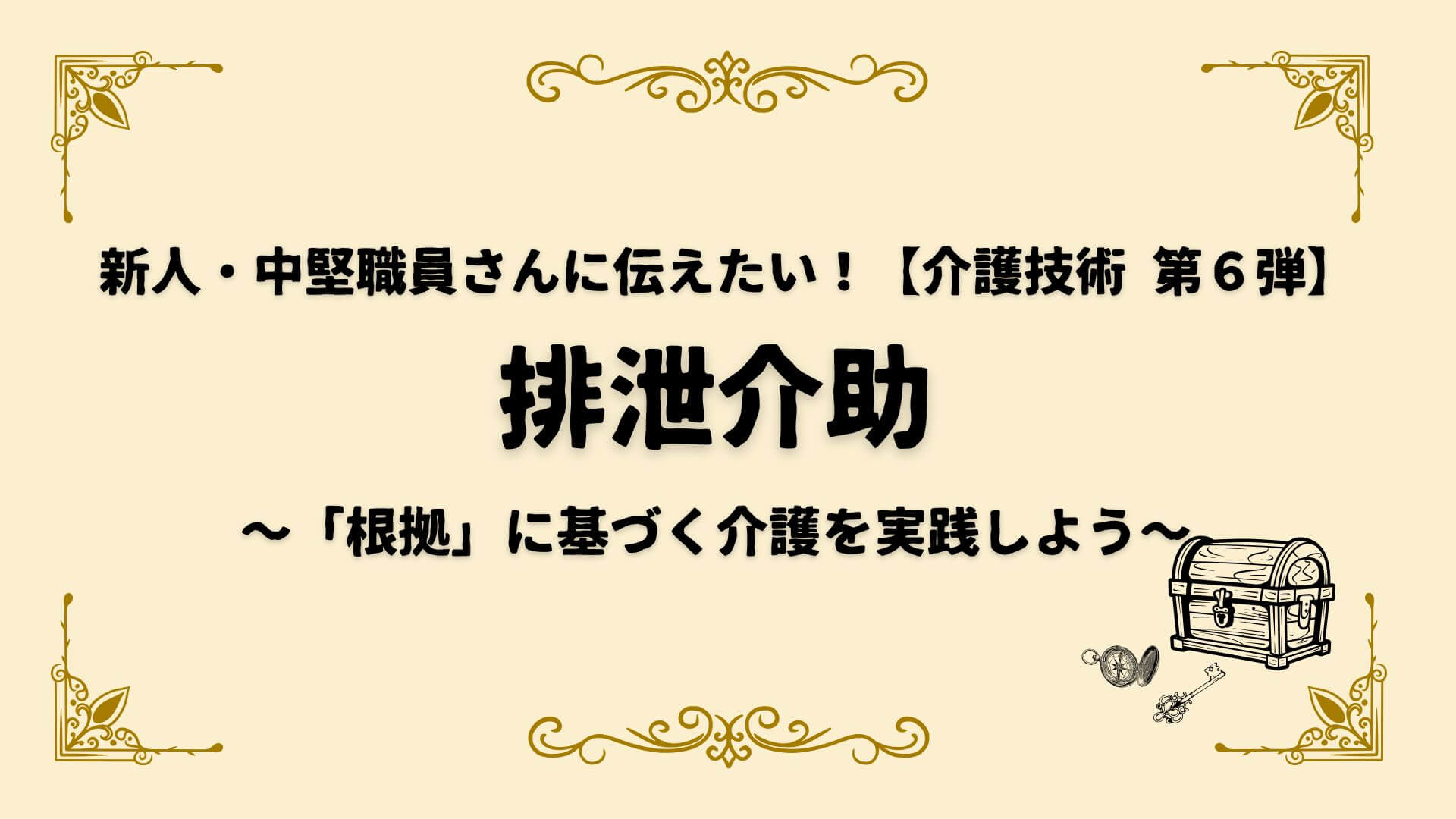
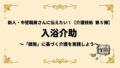
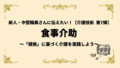
コメント