みなさんは、「正しい接遇やマナーを心がけましょう」「丁寧な言葉遣いをしましょう」といった言葉を、朝礼や会議、研修で耳にすることが多いのではないでしょうか。
介護の仕事をするうえで、当たり前のように求められることですが、実際のところ「自分の職場では接遇やマナーがちゃんとできている」と胸を張れる現場は、決して多くはないと感じています。
私自身、20年間介護の仕事に携わってきましたが、この「接遇やマナーをどうするか?」というテーマは、ずっと課題として残り続けています。
なぜ「大事だ」と言われ続けているのに、現場では徹底できないのか。そしてどうしたら改善できるのか。
今回は私なりの経験も交えながら、介護現場における接遇やマナーの必要性と改善のヒントについてお伝えします。
なぜ接遇・マナーが必要なのか?

利用者さんの尊厳を守るため
介護を受ける利用者さんは、身体的にも精神的にも不安を抱えていることが多いです。
だからこそ、敬意を持った態度や適切な言葉遣いで接することが、その方が「自分らしく」「ここにいてもいいんだ」と感じられる大切な支えになります。

ぞんざいな対応や乱暴な声掛けは、利用者さんの心を深く傷つけてしまうんだ。
利用者さんは「人生の先輩」であり「お客さん」
私たちは介護サービスを提供し、その対価として利用者さんから費用をいただいています。
つまり利用者さんは「お客さん」でもあるのです。また、介護の学校では必ず「高齢者は人生の先輩」と教わります。
「人生の先輩」「お客さん」――この二つの視点からも、接遇やマナーは欠かせないものです。
利用者さんやご家族との信頼関係を築くため
信頼関係があれば、利用者さんやご家族は困りごとを相談しやすくなります。
利用者さんが安心して過ごせる環境では、介護拒否や事故のリスクも減り、ご家族には「ここなら安心して任せられる」と思っていただけます。
安全で円滑なケアを提供するため
介護の仕事では、利用者さんに「食事」「移動」「入浴」などをしていただくために、「お願い」「お誘い」の声かけをする場面がたくさんあります。利用者さんにとって、身体的な負担が大きいことや納得できないことであれば、拒否されることもしばしば。
利用者さんが介助に協力してくださるかどうかは、信頼関係に左右されます。関係が築けていないと抵抗が強くなり、転倒やケガのリスクが高まります。逆に「この人なら安心できる」と思っていただければ、安全でスムーズに介護を進められます。

介護は利用者さんの身体に触れることが多いので、信頼関係が本当に大切!
自分に置き換えたら、信頼のおけない人に身を任せたりするなんて、恐ろしくてできないよね。
職場やサービス全体の質向上
接遇やマナーを意識することで職場の雰囲気は良くなり、人間関係や報告・連絡・相談もスムーズになります。その結果、施設全体の評判や職員のモチベーションも高まります。

家族や外部の方に「ここは雰囲気がいいですね」”って言われると、やっぱり嬉しい!褒められると、もっと頑張ろうって思えるよね
接遇やマナーが守られないのはなぜ?
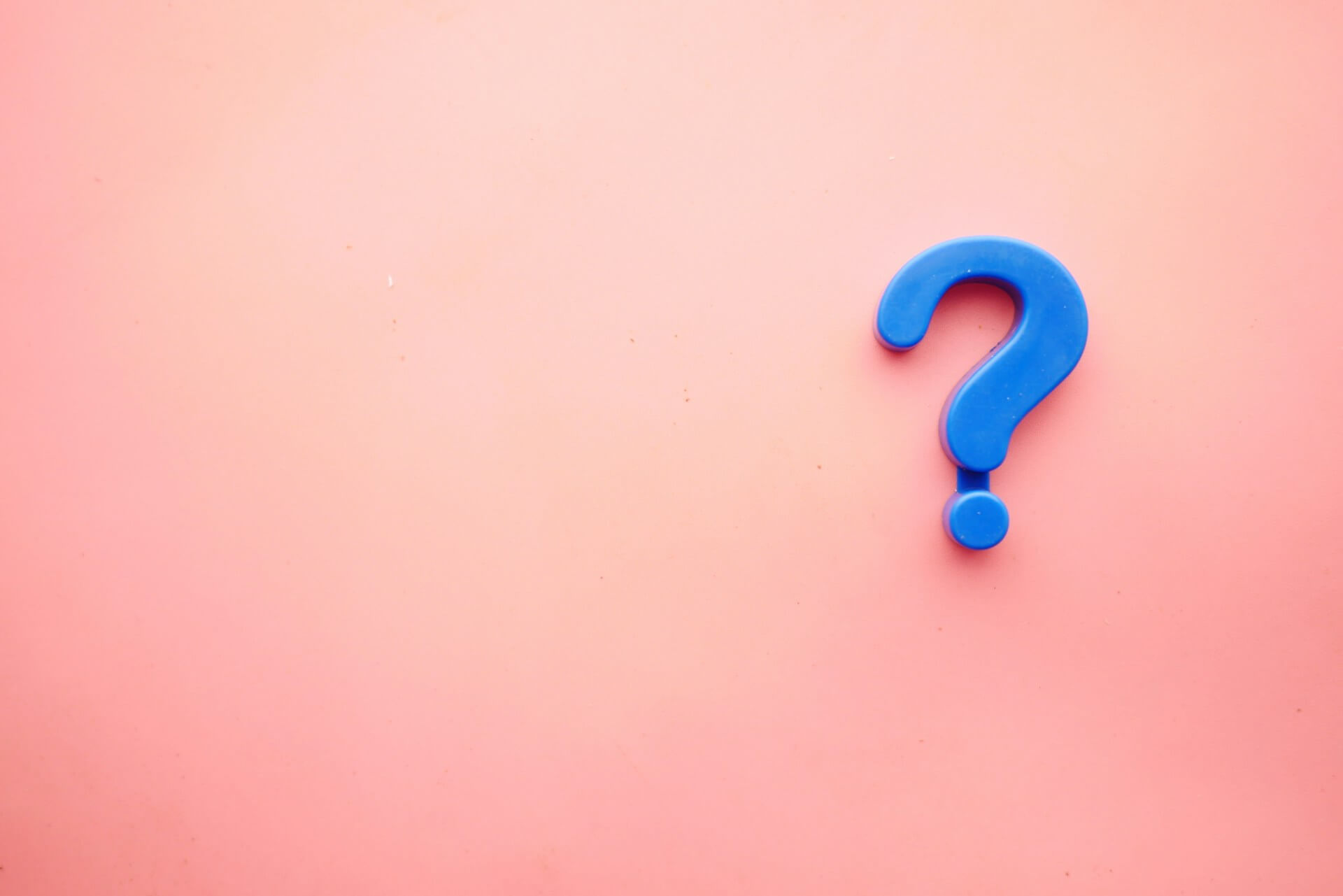
- 業務のいそがしさ・人手不足
- 教育・研修の不足
- 職員の価値観や意識の違い
- 職場の人間関係やストレス
- 業務の忙しさ・人手不足
忙しさから余裕をなくし、命令口調や乱暴な言葉が習慣化してしまう。
- 教育・研修の不足
新任研修や日常の指導が不足し、「最低限のサービス提供」にとどまってしまう。
- 職員の価値観や意識の違い
親しみやすさと馴れ合いを混同し、タメ口や子ども扱いが起きやすい。
- 職場の人間関係やストレス
雰囲気が悪くなるとマナーが軽視され、陰口やハラスメントの温床にもなる。

「人がいない」は言い訳にならないけど、気持ちの余裕がなくなると、ついつい早口になったり言葉が乱れたり…。

利用者さんに対して、「〜してあげてる」って感覚になってしまう職員も多いんだよね。
接遇やマナーが悪化するとハラスメントにつながる
マナーが低下すると、利用者さんへの無礼な態度や暴言、職員同士のハラスメント・いじめに発展する危険があります。
残念なことに、私の職場でもマナー低下による人間関係の悪化が原因で、退職に至った職員がいました。

「マナー低下」の根本原因のひとつとして「モラルの低下」があるよ。
モラルが低下すると、他者への配慮や社会規範を軽視するようになり、結果としてマナー違反の行動が増加するんだ。
マナーとは
他人を思いやり、社会で快適に過ごすための礼儀や行儀作法。守るべき行動が明確に決まっていることが多い
モラルとは
社会生活を送る上で守るべきとされる「善悪の判断基準」や「道徳観、倫理観」。個人の内的な規範

威圧的な態度、職場のルール無視、他者への共感の欠如…。
職員間の信頼関係は損われてしまうし、組織が機能しなくなるわね。

だから、「接遇を心がけること」や「マナーを守ること」は、ハラスメント防止の第一歩につながるんだよ〜
改善のためにできること

5原則を意識する
- 挨拶:自分から声をかける
- 言葉遣い:敬語・丁寧語を使う
- 表情:笑顔や温かい雰囲気を意識
- 態度:傾聴の姿勢、目線を合わせる
- 身だしなみ:清潔感と衛生管理

ここでも非言語的コミュニケーションが大事なのね!
チェックリストと振り返り
- 定期的に職員同士でチェックを行う
- 良い対応と改善点を無記名で共有し、朝礼や会議で話す

会議で“良かった対応”を共有すると、みんなが前向きになれるよ!
職場全体での教育・取り組み
- 新人研修や定期研修で意識づけ
- ロールプレイングやグループワークで実践的に学ぶ

聞くだけの研修はつまらない!みんなで体験する研修が効果的だよ。
最後に
接遇やマナーの向上は、一朝一夕で実現するものではありません。
「人手不足が解消されれば…」と思う方もいるかもしれませんが、私が思うのは、今ある環境の中で自分たちができることを積み重ねることが大事だということです。
たとえ小さなことでも、それを一つずつ積み重ねれば必ず現場は変わります。
利用者さんの尊厳を守り、安心できるケアを届けるために、今日からもう一度「接遇やマナー」を見直してみませんか?
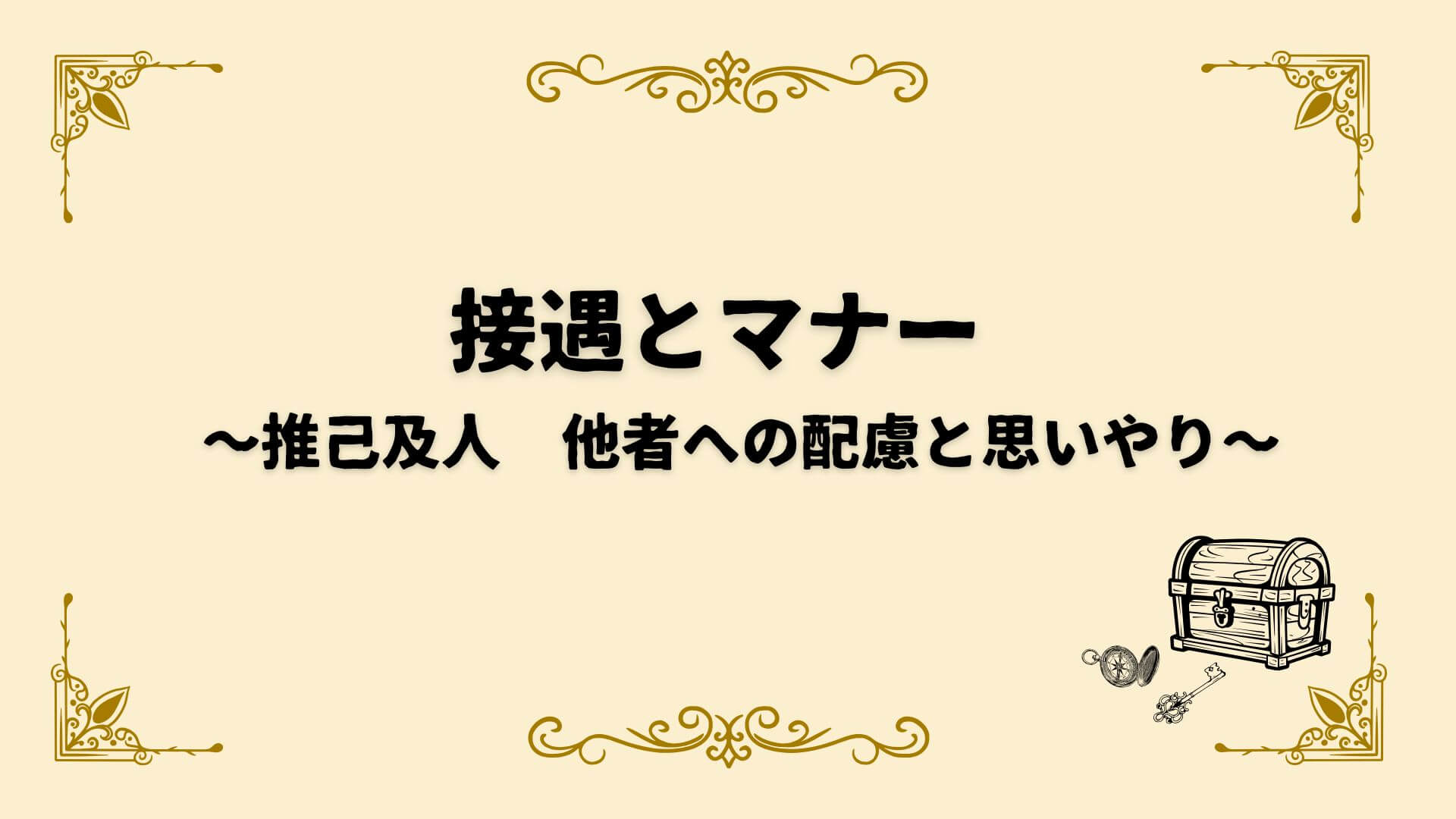

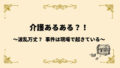
コメント