こんにちは まるです。実務者研修などで、介護技能実習生の指導をしてます。
介護の現場では、彼らの活躍が欠かせなくなってきました。
「自分の職場にも技能実習生いるよ〜」「一緒に働いてるよ〜」って方、大勢いらっしゃるのではないでしょうか?
勉強熱心で、仕事に対して前向きに頑張っている技能実習生ですが、その多くが「日本語が難しい」という悩みを抱えています。
この、お悩みに対して、私たち日本人スタッフがいい感じにサポートできたら、お互いに仕事をしやすくなると思いませんか?
今回は、技能実習生から聞いた「日本語にまつわるリアルな困りごと」と、それに対する具体的な支援のヒントを3つ紹介します。
これから、技能実習生を職場に受け入れる予定の方。参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
「日本語が難しい」をどうサポートする?意識すべき3つのポイント
「日本語が難しい」を、もう少し詳しく聞いたところ、
①漢字の読み書きが難しい
②声かけの言い回しが難しい
③わからないことを質問しても、答えてもらった日本語がよくわからない

わからないことを何度も聞くのも…。
よくわからないのに、ついつい「はい、わかりました」っていっちゃった
3つのことを意識して、それぞれのサポート方法を考えたら、上手くいきそうな気がしませんか?
漢字の読み書きが難しい
技能実習生が仕事をするうえで最初にぶつかる壁が、漢字の読み書きです。
特に「音読み」と「訓読み」の違い、熟語、当て字になると読み方が変わることに戸惑うようです。
「上」→うえ(訓読み)/じょう(音読み)、「人生」→「じんせい」など、文脈での判断が必要になる言葉。
「風邪」→かぜ や「明日」→あした のような当て字

新聞なんて、とても読めません(泣)

日本人でも新聞音読したら、「ん??」って、なることあるよ。母国語だけど、確かにややこしいよね。
漢字の意味と使い方をセットで伝える
たとえば、「排泄(はいせつ)」という言葉であれば、「トイレで出すこと」と意味を伝え、さらに「排」は出す、「泄」は漏れるという漢字がもつ意味や熟語の構成を簡単に解説します。
漢字がもつ意味を理解すると、読めない言葉でも、何を表現しているのか想像しやすくなるのは、日本人も同じですよね。
手書きよりも音声・イメージでサポート
写真、イラスト、ジェスチャーを使って単語や文型を教えると、日本語を直感的に理解できるようになります。
よく使う言葉をピックアップする
よく使う言葉を一覧にしたプリントを渡すと、困ったときにその場で確認したり、復習するときに役に立ちます。
浴室、トイレ、食堂など場所別の介護用語を一覧にしておくのも効果が期待できそうです。
声かけの言い回しが難しい
介護士といったら「介護技術とコミュニケーション力」。現場では丁寧で相手に寄り添った声かけが求められます。
「〜しましょうか」「〜されますか?」といった「やわらかい言い回し」や「遠回しな表現」は、日本人でも難しいことも。

(職場の同僚)
「遠回しな表現」にしすぎて、お年寄りに伝わらなかったり、
「敬語」で話していたら、「あんた冷たいわね!」っていわれたこともあるよ。
語尾や語調で印象も変わってしまうし、相手に合わせて言葉を選ぶスキルも求められるので、なかなかハードルが高いですよね。

優しい声かけ、失礼のない声かけをしたいけど…。
日本語の丁寧語、微妙なニュアンスの表現、方言…。どうすればいいの…。

日本人でも読み間違える言葉がたくさんあるよ。
方言も、きついとわからないしね。
シンプルな表現でOKと伝える
「トイレ行きますか?」「薬、飲みましたか?」のようなシンプルな声かけから始めるようにアドバイスすると、心理的なハードルを下げてあげられますよね。
慣れてきたら、少しずつ敬語をプラスしたり、別の言い回しを覚えてもらい、徐々にコミュニケーションの幅を広げていきましょう。
ロールプレイを活用して練習
1対1での会話練習や、実際の場面を想定した声かけ練習を日常的に取り入れると、表現力が身につきやすくなります。
表情やジェスチャーも大事に
言葉に頼りすぎず、笑顔やうなずきといった非言語コミュニケーションを併用することで、伝わり方が大きく変わります。
わからないことを質問しても、答えてもらった日本語がよくわからない
せっかく、わからないことを質問しても、相手から返ってきた答えの日本語が理解できず、質問することに対して消極的になってしまう人もいるようです。
また、「伝わらなかったらどうしよう…」「失礼に聞こえたらまずい」とか、何度も質問したら「迷惑になるのでは」「怒られるのでは」と不安に感じて、わからないことをそのままにしてしまうケースが少なくありません。
こちらが悪気なく放った言葉、特に態度は相手にとってプレッシャーになることもあります。
わからないことをそのままにして業務を行うのは、思わぬ事故につながる可能性があります。
「わからないことは聞いてね」と日常的に伝える
一度言うだけではなく、毎日のように「何かあったらいつでも聞いてね」と繰り返すことが大切です。
面談時には、技能実習生一人ひとりにあった「伝わりやすい方法」を相手と一緒に考えましょう。
質問しやすい雰囲気づくり
まずは、指導スタッフが積極的に関わり、「この人に聞いても大丈夫」と思ってもらえる信頼関係を築くことが必要です。
「伝わったよ」「ありがとう」など、こまめなフィードバックを行い、言葉や表情で相手に伝え、困っているときには、しっかりサポートしましょう。
あわせて、日本人スタッフには「この表現、難しくないかな?」「伝え方、わかりやすかったかな?」と、自分の言動を見直す視点を持つよう指導していきます。

講義の時は、普段よりゆっく〜〜りと話すように心がけているよ
技能実習生同士の支え合いも促す
同じ国の先輩実習生や、母語が共通するスタッフがいれば、自然と相談しやすい環境になります。
おわりに
日本語の壁は大きな課題ですが、現場でできる支援はたくさんあります。
技能実習生は、「日本語習得」と「わからないことをわからないと言える勇気」をもつこと。日本人スタッフは、「伝える工夫」と「相手を受け入れる姿勢」をもつこと。
お互い歩み寄りより良い人間関係を築いていきましょう!
介護の現場はチームワークが大切!
以上、この記事が少しでも皆さんの役に立てたら嬉しいです。
今後も、現場での実体験や講師としての学びをもとに、外国人介護職への支援について発信していきますので、よろしくお願いします!
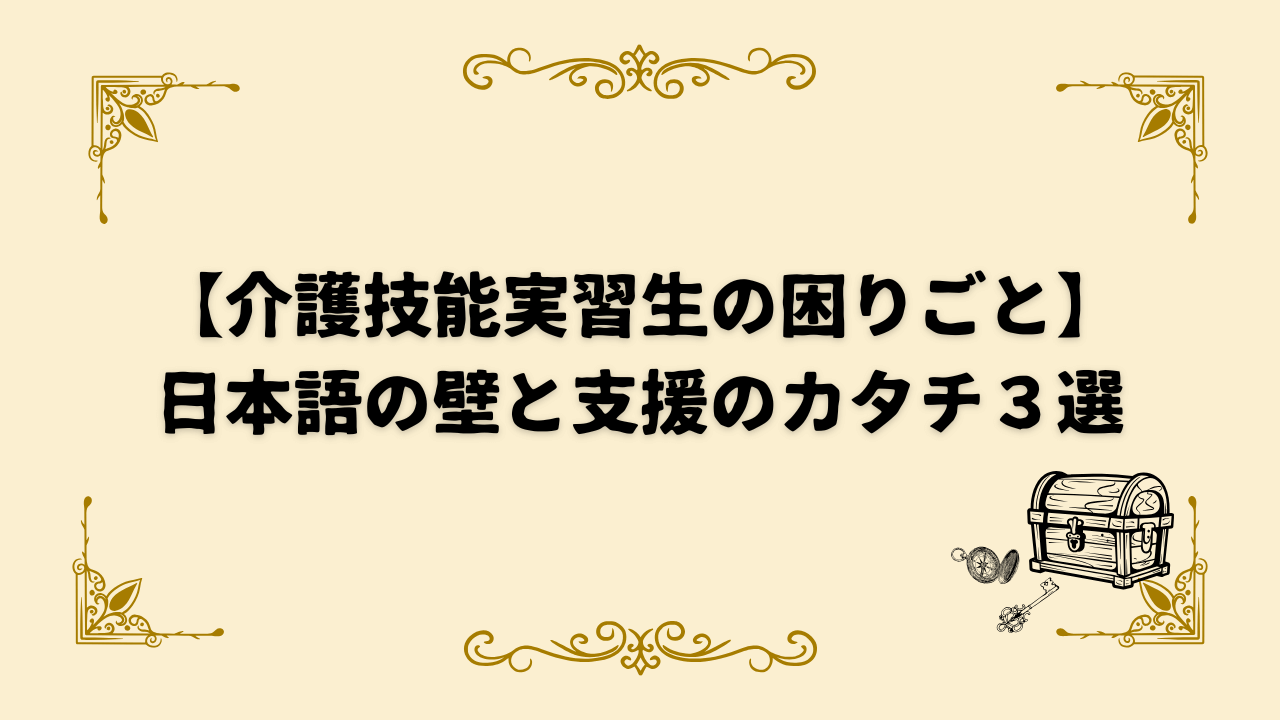
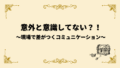
コメント